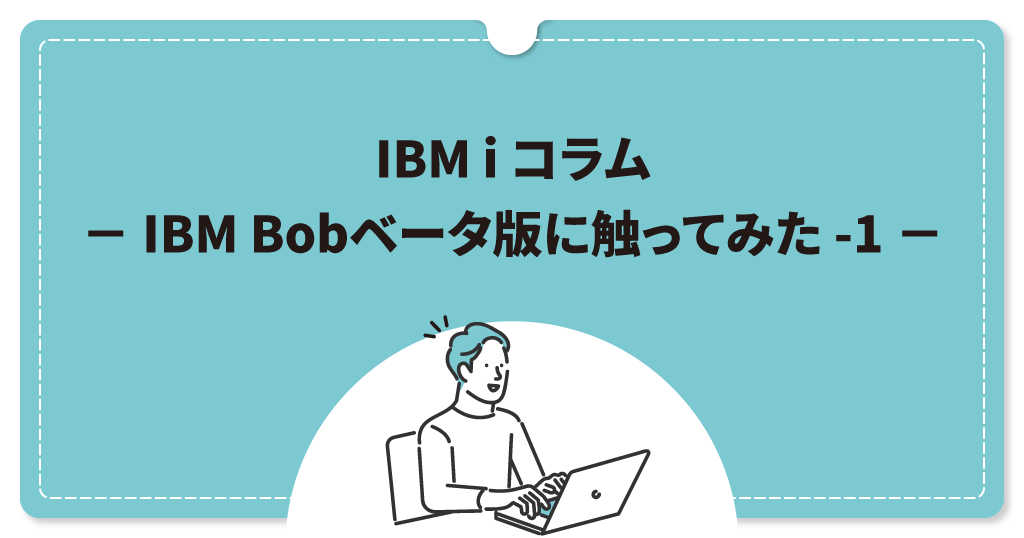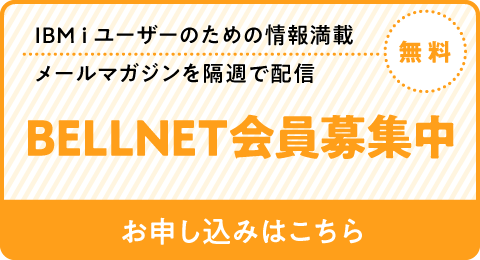IBM i のウンチクを語ろう:その41
- 情報通信白書で「2025年の崖」の背景を読み解いてみる -
皆さん、こんにちは。弊社ベル・データでは先の9月末をもって会計年度を締め、思いも新たに新年度をスタートさせたところです。お陰様で昨年度もビジネスは堅調に推移したようです。この場を借りまして御礼申し上げます。
私自身も毎年100回を超える機会をいただいて、セミナーや個々のお客様向けにIBM i 関連の講演を行っています。昨今関心の高い話題と言えば、IBM i を活用した「2025年の崖」の乗り越え方、でしょうか。「崖」という言葉は、ご存知のとおり、経済産業省が昨年9月に発表した「DXレポート」の中で、日本のITの将来に対する危機感を一言で表現したものです。
ITのパワーが効果を発揮する領域として、AI、IoT、アナリティクス(データ分析)など、世間ではDX推進の話題は頻繁に語られています。一方「転落」してしまっては元も子もないので、足元を固めるために「崖」対策も考えておく必要もあります。DXレポートでは、現行アプリケーションのブラックボックス化を回避するために、IT資産を分析評価して、機能毎に刷新、強化、廃棄・縮小、現状維持するべきものに色分けして、適宜対策を取る事を主張しています。ただサーバーを取巻く環境にも依存するため万能の手段はありませんし、レポートは具体的な方策には言及していません。さらに、システムを刷新するだけに留まっていては「崖」を一時的に先送りにするに過ぎないので、将来においてもシステムをブラックボックス化させないための、継続性ある予防策も考慮する必要があります。
IBM i の視点から「崖」対策を考える必要性は、このようなところにあるのかも知れません。第31回目の当コラム「2025年の崖』を乗り越えよう」において、IBM i の資産継承性という特徴を活かしながら、アプリケーション解析ツールであるX-Analysisを利用する案を紹介していますので、この機会にあらためて参照いただければ幸いです。ちなみに「崖」なので、本来は「転落しない」とか「避ける」が正しい表現なのでしょうけれども、消極的響きを感じるので、セミナー・タイトルなどでは敢えて「乗り越える」と表現しています。

経産省のレポートでは、アプリケーションのブラックボックス化と「崖」発生の理由として、SIerなど外部にIT技術者を依存する傾向が強く、社内に保守する体制が無いか弱体化している事を挙げています。何故そうなったのか、あまりきちんとは説明してくれていません。そこで毎年総務省が発行している情報通信白書(以下白書)を参照しながら、考えてみようと思います。日本のITの現状を網羅的にまとめたレポートで、最新の令和元年版は420ページにおよぶ大作です。いつもは関心あるところをつまみ食いする程度なのですが、第一節「ICTとデジタル経済はどのように進化してきたのか」に興味を引かれた次第です。ちなみにICTとはInformation and Communication Technology(情報通信技術)の事であり、実質的にITと同義と捉えて良さそうです。
今を去ること55年、1964年の日本では、東京オリンピックの記録配信や国鉄(日本国有鉄道の略称、現在のJRの前身)の座席予約のために、世界に例を見ないオンライン・システムが構築された、といった記述から白書の物語は始まります。続いて銀行・証券・運輸・製鉄など様々な業種における先進的なシステム導入が続きます。IT部門はマシンの単なる御守係から経営を支える役割を担う程に大きくなり、子会社として外部化する動きも出てきます。SIerの誕生です。ITが産業として成り立ち輸出額も伸びを見せ、日本は電子立国とも称されるようになります。この時点の日本のITは、間違いなく世界の先頭集団にいたのではないでしょうか。ちなみにDXレポートによると、ユーザー企業組織の一部を実質的に構成するように、ユーザーに代わってリスクを負いながら受託するという契約形態は、他国には見られない特徴なのだそうです。現在の企業数27,375、年間全売上高25兆円、従業員数97万人という、SI産業躍進の要因の一つになっていると思います。
1980年代になってもこの傾向はさらに進展するのですが、1985年のプラザ合意により円高ドル安圧力がかかり、次いで1991年のバブル崩壊を迎えると、日本経済はつまずきを見せるようになります。ITの世界に目を向けると、かつてのシステムは汎用機やオフコン(オフィス・コンピュータの略称、ビジネス専用の中小型システムでAS/400はこのカテゴリに入ります)など各ベンダーの固有技術で構築するのが一般的でした。1980~90年代になって市場で台頭してきたUnixやWindowsといったオープン・システムでは、技術の共通化ないしオープン化へのシフトが進み、ハードウェアやソフトウェアの初期コストは大きく下落します。参考までに旧来のシステムも、オープン性を取り込む事で生き残ったものと、そうでなかったものとに明暗が分かれます。IBM i はAS/400の発展形として生き残り組に留まっている事はご存知のとおりです。
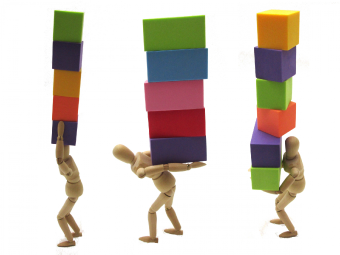
さて、厳しい経済環境の中にあって、多大なコスト削減圧力を受けていた企業にとっては、新しいシステムは魅力的に映ったはずです。汎用機やオフコン全盛期は、これらシステムが比較的生産性の高い開発ツールを備えていたり、SIer社数も多くはなかったという環境上の事情もあったりして、ユーザー企業が業務アプリケーションを自力開発するのはごく一般的に行われておりました。オープン・システムになると、アプリケーションを一から開発するための技術力を備えると同時に、コストと手間を賄える企業はなかなかありませんので、出来合いのパッケージを導入する事になります。そのままで各企業の業務に適合する事はないために、前提としてカスタマイズ作業を行わなくてはなりません。ユーザー企業が自力で実施するのは極めて困難ですので、外部のSIerに依存する事になります。ITを生業としない企業にとって、中核事業ではないITはできるだけコストと手間をかけずに済ませるべき、という考え方がこれに拍車をかけます。
それまで拡大傾向にあったIT投資は縮小に向かいます。白書のページ62のグラフ「日本のICT投資額の推移(名目)」によると、一時的に回復し1997年にピークを迎えた後は、今日に至るまで減少傾向から脱しておらず伸び悩んだままになっています。動向を海外と比較してみると、その停滞ぶりはより一層顕著なものになります。同じくページ62にあるグラフ「各国のICT投資額の推移比較」を見ると、1980~95年にかけてのIT投資の伸びは日本・アメリカ・イギリス・フランスとも同程度に推移しています。ところが2017年時点での1995年に対する比率は、イギリスは約1.5倍、アメリカとフランスは約3倍と大きく成長しているのに対して、日本はほぼ同じレベルに留まります。白書ではGDPの伸び悩みと関連している可能性があるとも指摘しています。

量だけではなく日本のソフトウェア投資の内訳を見てみると、パッケージが11.7%、カスタマイズないしスクラッチによる受託開発は88.3%、と外部に開発を委託する割合が極めて高くなっています。自社の既存業務を不変のものとし、カスタマイズありきで開発するために、パッケージに備わっているせっかくの優れた業務プロセスが実装されないケースがあるかもしれません。自社業務に必ずしもフィットしないアプリケーションが開発され、失敗プロジェクトでありながらも、止むを得ずそのまま導入されてしまうケースもあるかもしれません。アメリカでは集計されている自社開発の数字を見るとトップの37.2%を占めており、受託開発33.8%、パッケージ29%と続きます。集計対象が異なるので日本とアメリカとで単純比較はできませんが、自社業務をサポートするためのIT投資における姿勢の違いはありそうです。
かつての日本はIT先進国であったにも関わらず、円高圧力とそれに伴うバブル崩壊を契機としてIT投資抑制と外部委託化が進みました。その結果DXを推進できないままに、座して「崖」から転落するのを待つ状況に陥りかけている、というのがDXレポートの警告です。冒頭に述べたように、アプリケーションのブラックボックス化の兆候が見られるようになっても、IBM i ならば回避するためのツールがあります。DXアプリケーションを構築するための環境も内包されています。製品内部に隠蔽されている複雑なテクノロジーには一切関知せずに、ユーザーは様々なソリューションを活用できるようにする、という製品戦略がもたらすメリットです。「崖」転落を回避しながらDXを推進いただければと思います。
ではまた