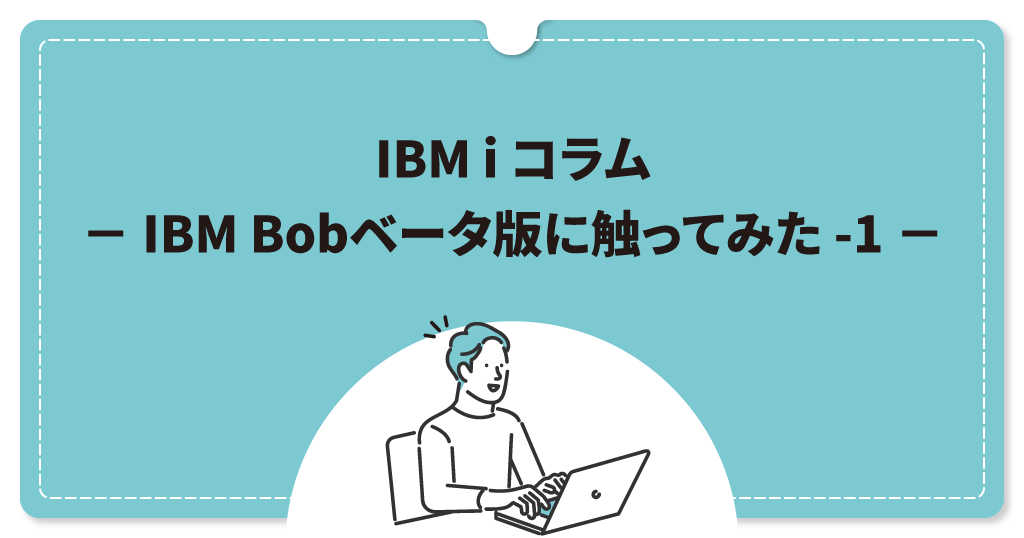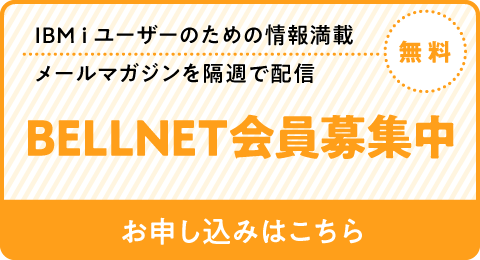IBM i のウンチクを語ろう:その40
- IBM i の戦略はデジタルトランスフォーメーションのために -
皆さん、こんにちは。IBM i の新バージョンが登場すると、ホワイトペーパーが刷新され、最新の製品戦略が詳らかになります。先日のIBM i 7.4発表に伴って、英語版は既にリリースされていたのですが、9月初めにようやく日本IBMより翻訳版が公開されました。今回のこのコラムではポイントをいくつか簡単に紹介したいと思います。なお、英語原文と翻訳版とを読み比べ、さらに適宜安井個人の解釈を加えながらこのコラムを書き進めていきますので、言葉遣いなどにおいて必ずしも翻訳版に忠実ではない事を、あらかじめご了承ください。
IBM i のお客様をどのように理解するのか、という点から戦略策定は始まります。キーワードとなるのはデジタルトランスフォーメーション(以降DX)です。日本においても昨年9月に経済産業省がこれをテーマにしたホワイトペーパー「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」を公開した事はご存知と思います。詳しくは第31回目のIBM i コラムでも紹介していますので、あらためて目を通していただければ幸いです。レポート中に登場する「2025年の崖」という言葉は有名ですね。「崖」の認識は日本特有のものですが。

さて、企業はDXに真剣に取り組んでいる、DXはITが成し遂げるべきものの一部である、といった仮定に基づいて3つのIBM i 重点分野が定められています。最優先事項としてのソリューション、幅広い選択肢を提供できるオープン性、そして統合性、です。
ソリューションとは、直訳的に考えればビジネス上の課題を解決するためのものであり、より具体的にはISVによるソフトウェア・パッケージや、個々のユーザー向けに開発されるアプリケーション・プログラムも含んでいます。IBM i とは言ってもソリューションが無ければただの箱だというわけです。
今日の優れたソリューションは多様な技術を必要とします。例えばRPG言語のみで記述された販売管理アプリケーションのようなものを想定しているわけではありません。外部からブラウザで在庫照会できるようにするためには、RPGに加えてPHPやJAVAテクノロジーが必要になるかも知れません。REST APIを利用して発注処理を行う可能性もあります。これらの裏側ではSQLインターフェースによるデータベース・アクセスが行われますし、多様なテクノロジーを自在に活用できるアプリケーション開発ツールも必要です。もはや単一のテクノロジーだけでソリューションを開発する時代ではありません。そして様々な優れたソリューションを実現するために、テクノロジーの選択肢を拡充する事は、オープン性を追求する事でもあります。
IBM i のオープン性と聞くと違和感を覚える方もいらっしゃるかも知れません。一般的にはIBM i は「レガシーシステム」であって、「オープンシステム」のカテゴリには入らないからです。この是非はさて置くとしても、重要なのは多種多様な業界標準テクノロジーを実装できる事・する事であって、サーバーのカテゴリではありません。そしてIBM i は20年以上にわたって、オープンな技術を統合してきたとホワイトペーパーは述べています。安井個人の理解では、31年以上に及ぶIBM i の歴史におけるオープン化への転換点は、1995年に旧来のCISCプロセッサからRISCプロセッサ採用へと大きく舵を切った辺りにあります。当時は未だAS/400と呼ばれていた、独自色の強いシステムの将来を考えた時に、いずれ必須となる様々なオープンなテクノロジーを取り込むためには、プロセッサの刷新は技術的必然でした。この辺りの事情について詳しくは、当コラムの第29回と第30回「過去30年の間に最も大きく変わったもの」を参照ください。

オープン性実現の顕著な動きは、各種のオープンソース・テクノロジーの取り込みに見られます。例えば第36回のコラム「IBM i 7.4登場」にあるように、IBM i の最新バージョン7.4のハイライトの一つでもあります。パッケージ管理のyumやRPM、プログラム言語のR、Node.jsやPythonなど、実装できるソリューションに多様性が生まれるだけでなく、旧来のRPGやCOBOL言語の利用経験の無い、若い人材をIBM i コミュニティの中に呼び込む効果も産まれています。
多様性は複雑さにもつながります。機能毎にサーバーを用意し、それぞれを連携させようとしたら、各機能の互換性を理解し、バージョンアップ等の変化を管理しなければなりません。お客様は技術力を磨き、技術動向に常に目を向けていなければなりませんし、さもなければコストをかけて外部に委託する事になります。
お客様はビジネスに集中する事に関心があるのであって、ITを管理するのは本来は二の次であるはずです。テクノロジーを剥き出しの状態に置いておくのは望ましくありません。IBM i が製品戦略として三番目に掲げるのは、多様性からくる複雑さを可能な限り製品の中に押し込め統合し、隠蔽してしまう事です。テクノロジーの管理はメーカーの仕事であって、お客様のものではない、という発想です。
IBM i の三つの製品戦略は一体となって、お客様のDX推進をバックアップします。ホワイトペーパーのサブタイトルにある「変革者のための」(英語版を直訳すると「イノベーターのための」)の意味はここにあります。ホワイトペーパー分量は全20ページ、三つの製品戦略部分のみならば実質2ページにも満たない分量です。また、IBM i 各バージョンの寿命を長期的に示す「IBM i サポート・ロードマップ」も掲載されていますので、是非読んでみてください。

このコラムの書き出しのところで、「企業はDXに真剣に取り組んでいる」事を「仮定」であるとしました。ホワイトペーパー原文では、単に事実認識として記述したに過ぎず、仮定とか前提といった言葉を用いていません。日本特有なのかも知れませんが、DXの狙いとするべき点が必ずしも正しく理解されていないケースが報告されており、一度点検してみていただければと思う次第です。
経済産業省管轄下の独立行政法人に、情報処理推進機構という団体があります。IPA(Information-technology Promotion Agency, Japan)の方が通りが良いかも知れません。今年5月にIPAが公開したレポート「デジタル・トランスフォーメーション推進人材の機能と役割のあり方に関する調査」のページ13に、「現在取り組んでいるDXの内容」というグラフがあります。DXの本来の趣旨は、ここで言うところの「新規製品・サービスの創出」や「現在のビジネスモデルの根本的な変革」に該当するはずなのですが、残念ながらこれらへの取り組みは全体の半数以下に留まっています。約8割と最多数の「業務の効率化による生産性の向上」は、実際にはDXというよりも、旧来から取り組んできた改善活動に過ぎません。IT系のメディアの中には、この取り組みはDXを理解していない、と指摘するものもあります。 DX のつもりなのだが実は本来のDXではなかった、というのは避けたいですね。
今回は戦略という、やや抽象的なテーマを取り上げてみました。IBM i への取り組みを通じたIBM社の姿勢、並びにIBM i へのより良い理解と、DX 取り組みの再点検のきっかけになれば幸いです。
ではまた