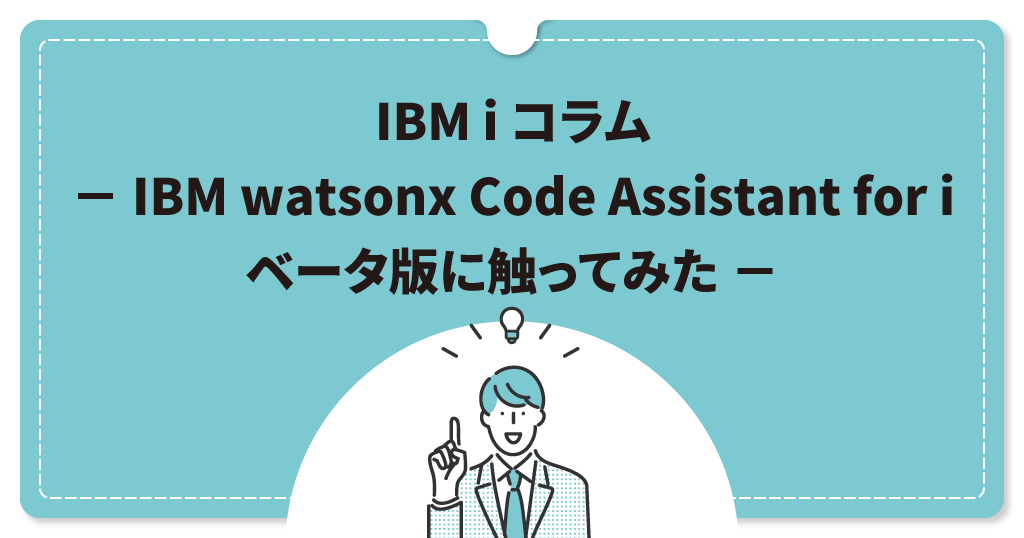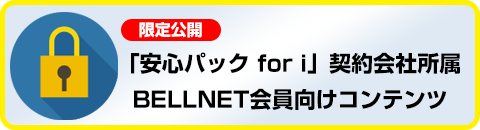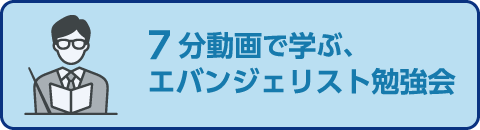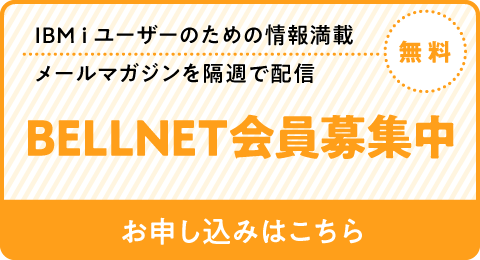IBM i のウンチクを語ろう:その113
- ちょっとわかり難くなったかもしれないIBM i 7.4終焉の発表 -
皆さん、こんにちは。どのようなものであれ、変化はストレスであるのは普遍的な事実だと思います。ただ、自らその必要性を理解して積極的に受け入れる時のポジティブなストレスと、外的要因によって希望とは合致しないことを受け入れざるを得なくなるネガティブなストレスとでは、当事者の心持は全く異ってくるものです。製品発表についても同様のことが言えるでしょう。そしてたとえ好ましからざるものであったとしても、その内容を認知・理解し早期に対策を講じる準備を始めなくてはならないものの代表例は、サポート終了に関するものです。IBM i バージョン7.4の営業活動終了が2026年4月30日、そして標準サポート終了が2026年9月30日、と先の9月16日に発表されたことをご存じの方もいらっしゃることと思います。
その発表レター「マーケティングからの撤退とサービス・レベルの変更: IBM i 7.4 ポートフォリオとオファリングおよび機能の追加撤退」はタイトルが長いだけでなく、言葉遣いが従来とは異なっているので、意味がわかり難いかもしれません。「マーケティングからの撤退」は英語版発表レターの中の「Withdrawal from marketing」に忠実な訳になっていて、実質的に「営業活動終了」を意味することは違和感無く受け止められるでしょう。この部分は従来どおりですし問題無いと思います。しかし「サービス・レベルの変更」、英語原文では「change in service level」は直訳としては妥当でも、従来言うところの標準サポート終了を意味するようには見えません。一切のサポート提供を終了するのではなく、標準サポートから延長サポートへとその内容を変更する旨を明確にした、実情に合った言葉遣いに切り替えたという意図のようです。開発部門は、今後はこの新しい用語を採用するとしています。
さてここであらためて、サポート終了の発表に関するIBMのポリシーを確認しておきましょう。方針とか原則論といったようなものです。私の知る限り過去20年近くにわたって維持されているのですが、その一部はあまり認知されていないかもしれません。出荷開始から延長サポート終了までの、いわゆるライフサイクルを一覧にした以下表を参照しながら話を進めてゆきたいと思います。念のためですがこの一覧は、開発部門が公にしているIBM i の「Release life cycle」ページ(英語)から、バージョン6.1以降を対象に抜粋・編集したものです。
| バージョン | 出荷開始日 | 標準サポート終了 発表日 |
標準サポート終了 発効日 |
延長サポート終了 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 7.6 | 2025/04/18 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 7.5 | 2022/05/10 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 7.4 | 2019/06/21 | 2025/09/16 | 2026/09/30 | 未発表 |
| 7.3 | 2016/04/15 | 2022/09/27 | 2023/09/30 | 2028/09/30 |
| 7.2 | 2014/05/02 | 2019/09/10 | 2021/04/30 | 2026/04/30 |
| 7.1 | 2010/04/23 | 2017/04/11 | 2018/04/30 | 2024/04/30 |
| 6.1 | 2008/03/21 | 2014/09/09 | 2015/09/30 | 2019/09/30 |
まず気になるのは製品寿命の長さでしょうか。IBM i に対するIBMとしての製品戦略を明らかにするホワイトペーパー「IBM i: 統合と革新」のページ20では、出荷開始を起点に、標準サポート7年間とその後の延長サポート3年間、合計10年間がこれまでの実績であると述べています。上記表を見ても、確かに7年間以上の標準サポート期間が確保されています。これに続く延長サポートについては、6年間に及んでいるバージョンもありますが、ホワイトペーパー上は文章として表現されていないこともあり、原則3年間と見なすのが良いでしょう。これは延長サポートの発表のされ方によるものです。延長サポートは標準サポート期限近いタイミングで発表され、その期間は3年間です。その後さらに市場動向を見ながら、必要に応じて追加延長サポートが発表されています。その期間は必ずしも一定していませんが、例えば直近のバージョン7.3に関しては2年間です。すなわちIBM i のサポート期間は7+3年が基本であり、状況によって7+3+2年またはそれ以上になる可能性がある、というわけです。
最後の2年間は別にして、7+3年間というサポート期間は「過去の事例」であると上記ホワイトペーパーに表現されていることに留意したいと思います。標準であれ延長であれ、サポート期間はその時のビジネス状況を見極めた上で都度判断されるため、将来に対するコミットメントとはされていません。だからと言って、長年積み重ねてきた実績でもあるので、よほどのことが無い限りこれがいきなり大きく変わることは無いと思いますが、公式にはその可能性は排除されていないということです。
ちなみにこのホワイトペーパーは2024年8月付けとページ3に示されていますが、誤植のようです。IBM i 7.6がページ19-20の図に反映されているので、実際にはこれが発表された2025年4月か、それ以降のタイムスタンプでなくてはならないはずです。旧版に手を入れる際に見落とされたのでしょうか、この点はちょっと惜しいですね。
IBM i のようなIBMにとっての主要製品については、標準サポート終了の発表日から発効日まで12カ月以上の期間が確保される、というポリシーもあります。いきなりサポートが打ち切られることが無いことは、基幹業務システムを運用する立場からすると安心材料の一つだと言えるでしょう。
少々地味ではあるのですが、サポート終了日は4ないし9月末とする、というポリシーもあります。従来は製品によってその日付に統一性はありませんでした。憶えにくいだけでなく、システム全体を管理するのが煩雑になるという問題があったため、このいずれかの日に統一されることになっています。
最初に掲載したスケジュール一覧をあらためて眺めると、これまでに述べてきた全てのポリシー通りに推移していることがおわかりいただけると思います。製品利用において安心感があるのではないでしょうか。企業の基幹業務を支えるサーバーであるという位置付けが、地味ながらこのような形で具現化されているのですね。
続いて延長サポートの期間と料金について概要を見てみましょう。実際には市場の状況に応じて都度策定されることになっているのですが、再び直近のバージョン7.3を例にとってみます。参照するのは延長サポートのガイド「Service Extension for IBM i 7.3 and 7.2」(英語)です。目安にはなると思いますが、バージョン7.4にそのまま適用される保証はありませんので、その点はご注意ください。
延長サービスの内容は二段階で示されています。まずは3年間の「最初の延長」(上記英語ガイドにおける「First extension」)が標準サポート期限間際に発表され、その後2年間の「(さらなる)延長」(同「Extended」)が追加発表されています。これらが上記で言うところの3+2年間に該当します。
料金についてですが、ソフトウェア・メンテナンス(SWMA)契約が締結されていることを前提として、これに対する倍率で延長サポート料金が定められています。倍率は以下のとおり、標準サポート期限後の年数に応じて大きくなります。念のためですが、4年目・5年目は同額です。
- 1年目:SWMA料金の2.5倍=SWMA+SWMAの1.5倍の延長サポート料金
- 2年目:SWMA料金の3.0倍=SWMA+SWMAの2.0倍の延長サポート料金
- 3年目:SWMA料金の3.5倍=SWMA+SWMAの2.5倍の延長サポート料金
- 4年目:SWMA料金の4.0倍=SWMA+SWMAの3.0倍の延長サポート料金
- 5年目:SWMA料金の4.0倍=SWMA+SWMAの3.0倍の延長サポート料金
IBM i の新バージョンが登場すると必ずと言って良いほどお客様からいただく質問の一つに、出荷開始からどの程度の期間を経過したら品質が安定するのか、というものがあります。結論から言いますと、バージョン対応などの面において制約が無いのであれば、敢えて古いバージョンを選択する必要は無いと考えています。
理由の筆頭に挙げられるのは新バージョンの品質です。かつてのIBM i の開発においては、最初に英語などのシングルバイト(SBCS)版が手掛けられ、次にそれを日本語などのダブルバイト(DBCS)版に変換する、という手順を踏んでいました。この変換というプロセスにおける問題のためかDBCS版独自の問題が生じることがあったために、新バージョンが他の日本のユーザーにどれだけ浸透しているのか、というのが採用に際しての大きな関心事になっていました。いつ頃だったのか正確には憶えていないのですが、この開発手順は20年以上前にDBCSを基準にするよう変更されており、以降は日本語環境固有の問題が生じるケースは激減しています。また、ベル・データでは新バージョン登場の都度、可能な限りベータ・プログラムに参画するようにしているのですが、品質的に極めて安定しているという印象を持っています。
もう一つは製品寿命やサポート料金に関わるものです。先のスケジュール一覧に見られるとおり、バージョン7.4と以降のバージョンの登場サイクルは3年です。後継バージョンが既に利用可能であるにもかかわらず3年前のバージョンを採用するということは、利用中に延長サポート期間に突入してしまい、より高額なサポート料金を発生させる可能性や、場合によってはあらゆるサポートが提供されなくなるリスクを抱え込みます。もちろん最新機能を利用できないというデメリットもあります。
以上IBM i 7.4のサポート終了の発表を解説させていただきました。新テクノロジー採用のきっかけにする、というポジティブな姿勢でバージョン・アップグレードを検討いただければ幸いです。
ではまた