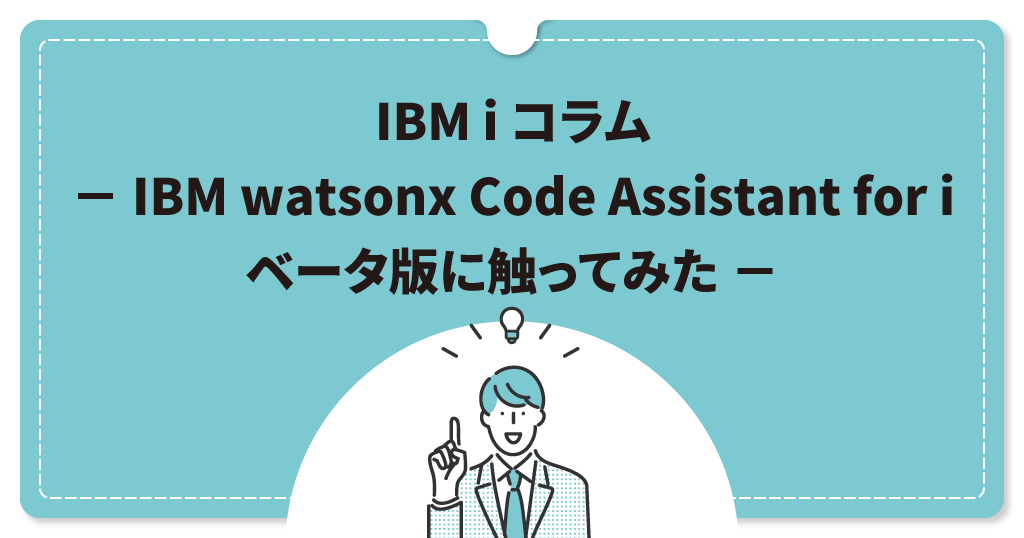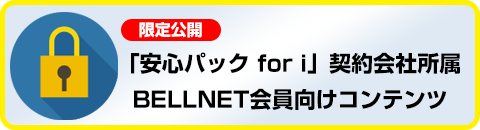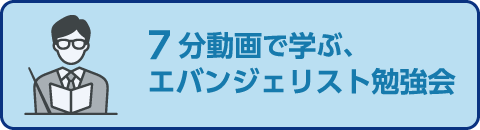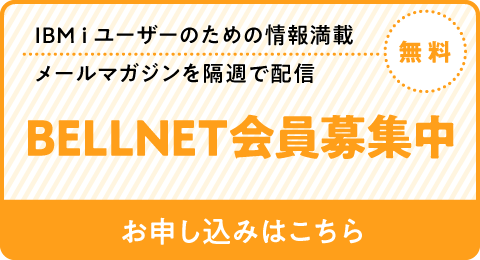IBM i のウンチクを語ろう:その109
- 「2025年の崖」はどこに行った? -
皆さん、こんにちは。「DX」という言葉が世間に認知されるや否や、個々人や各企業による独自の定義・解釈がいくつも生まれた、いわゆるバズワード化するきっかけとなったのは、経済産業省が2018年9月7日に公開した「DXレポート ~ITシステム『2025年の崖』克服とDXの本格的な展開~」という文書でした。そしてこのタイトルの中でひときわ目を引いたのは、メインテーマのDXよりもむしろ「2025年の崖」の方だったのではないかと思います。日本の産業界全体を覆い尽くしてしまうであろう厄災が2025年に到来することを示唆するような、お役所らしからぬ煽り気味の言葉遣いは、IT業界内外を問わず極めてインパクトのあるものとして受け止められました。
2025年も早くも半ばを過ぎ、いよいよ崖が眼前に迫ってきたと喧伝されるわけでもなく、これまでと同様に今後も時は静かに刻まれてゆくように感じられます。たまに周囲でも話題になるのですが、「崖」はどこに行ってしまったのでしょうか。実は気付かぬうちにすぐ眼前に迫っているのかもしれませんし、何年かの遅れが生じているのかもしれません。もしそうだとしたらそれはいつなのか、経済産業省は新たな事実を明らかにするべきではないか、という疑問も生じます。

そもそも経済産業省は何をもって「崖」の到来を2025年(より正確には2025年末)としたのでしょう。デジタル市場の拡大を背景にしながら、2025年には基幹システムの60%が稼働開始後21年以上、IT人材不足が43万人にも達するという予想がありました。さらにWindows Server 2012(サポート終了日は2023年10月10日)やISDN(同2023年末)に続いて、SAP Business Suite 7のサポート提供が2025年末までとされていました。これが「2025年の崖」に直結していたようです。ところが「崖」の原因になったと非難されることを恐れたわけではないでしょうけれども、DXレポート公開から約1年半後の2020年2月4日に、SAP社は件の製品の標準サポート終了日を2027年末まで延期し、さらに延長サポートを2030年末まで提供すると発表しています。この時点で「2025年」は根拠の何割かを失ったまま、「2030年」に改められることも無く、墓標(?)のように忘れ去られかけた存在になってしまいました。
では「崖」とはどのような厄災なのでしょう。担い手不足などが原因で保守・運用が行き届かなくなったレガシー・システムにおいて、セキュリティ事故や災害などによりトラブルやデータ滅失が生じてしまい、日本全国の経済損失総額が12兆円にも達する危機を言います。DXレポート公開当時の損失額が、3倍に膨れ上がるという試算です。「崖」から転落してしまうほどの急激な変化と言うよりも、時間をかけて次第に長い下り坂を転がり落ちてゆく、という表現の方が合っているようです。だからと言って「2025年の下り坂」では全くインパクトを感じませんね。そして、どこが底なのかがわからない、ゆっくりとした変化なので明確にそうと意識されにくい、という意味では想像以上に厄介かもしれません。2030年になったらなったで2025年よりも状況はさらに深刻になっている可能性すらあります。よく言うところの「茹でガエル」状態です。もっとも実際のカエルは徐々に水を茹でたとしても逃げる時は逃げるそうなので、この話は都市伝説らしいですが。
さて、DXレポートでは「崖」を回避するためにレガシー・システムからの脱却が必要だとしていたのですが、この表現はIBM i にとって極めて強い逆風になっていました。レガシー・システムとはオープン系以外のシステム、すなわち旧来のメインフレームやIBM i のことだ、といった理解が広まっていたために、これらはDX推進の阻害要因になるので急ぎ脱却しなければならない、というわけです。業務を支える手段として位置付けられているにもかかわらず、DX推進という名目のもと、ITを刷新すること自体が目的化してしまうケースも目立つようになりました。その多くはITの問題やその深刻さの評価という、ごくあたりまえのプロセスを経るものではありませんでした。何かのブームが到来すると、正攻法的思考は隅に押しやられてしまうこともある、といったところでしょうか。

これに対して例えば有名な調査会社であるGartner社は、「IBMのレガシー・プラットフォームからの脱却は、品質をリスクに晒すにもかかわらず、期待したほどのコスト削減効果は見込めない」(公開記事の一部を安井訳)といった見解を出しました。さすが冷静かつ論理的な見解だ、わかっている人はわかっている、と勝手に感心しておりました。当の経産省もDXレポートにおける言葉足らずを感じたのか、その後に公開された追補版において、DXとはレガシー・システムからの脱却のことではない、という見解を明らかにしたのですが、世間の理解を修正するには至っていないと思います。一度定着してしまった第一印象を覆すのは難しいものです。
「2025年の崖」はどうなったのか、という問いを放置しておくわけにはいけないと感じたのか、先の5月28日に経産省は「DXの現在地とレガシー・システム脱却に向けて」という文書を公開しています。「DXの現在地」とあるので、「崖」について何らかの回答めいたものがありそうですね。実際のところ何が主張されているのかいくつかポイントを拾ってみましょう。
冒頭に現状認識として、「DXおよびレガシー・システム脱却の進捗は依然としてスピード感に欠ける」とあります。これがこの文書の最大のポイントの一つなのでしょう。かつて「崖」に直面するぞと警鐘を鳴らしたにも関わらず、産業界における進捗状況はよろしくないというわけです。ユーザー企業の61%がレガシー・システムを保有しており、特に大企業においてその割合が高い(74%)というデータが示されています。レガシー・システムからの脱却をもってDXの進捗と見なすのはいかがなものか、相も変わらず手段と目的の取り違えを助長するつもりなのか、という疑念を抱いたのですが、レガシー・システムの定義を述べているページがあることに気付きました。これまでに触れられてこなかった点ではないかと思います。
件の文書のページ7にあることを簡単にまとめると、レガシー・システムとは、保守や機能改善が困難であるために、コスト高で経営上の足枷となっているシステムです。技術が老朽化しており、肥大化・複雑化したためにブラックボックス化し、投資がなされないままに古い制度に縛られていることが要因になっているとされます。そして我々にとっては重要なポイントになるのですが、メインフレームをその代表格としてはいるものの、メインフレームだからレガシー・システムだ、といった短絡はされておりません。そして、技術の新旧が問題なのではなく、仕様が明確できちんと保守されており、データ連携や継続的な機能強化が可能になっていれば、レガシー・システムではないとしています。逆にメインフレームから脱却していても保守が行き届いていなければ再レガシー化してしまう、と指摘しています。ちなみにこの文書においては、IBM i はメインフレームの一員として見なすべきでしょう。

「DXの現在地」に関しては、文書ではレガシー・システムからの脱却が進んでいないという現状認識に留まっていて、「2025年の崖」の行方はそれ以上追求されていません。2025年一杯を乗り切れたら大丈夫というわけではなく、影響の出方は各企業によって様々ではあるものの、「坂道を継続的に転落中」と見なすべきなのではないかと思います。そして「レガシー・システム脱却」のために企業は何を実践するべきか、そのための施策に多くのページが割かれています。精査はしていませんが、これまでのいくつかのバージョンのDXレポートにおける主張の集大成と思えば良さそうです。私もこれまでの当コラムにおいて何度か言及していますので、よろしければ以下を参照いただければ幸いです。
「2025年の崖」を乗り越えよう
DXレポート2を読んでみた Part 1
DXレポート2を読んでみた Part 2
DXレポート2.1を読んでDX推進のきっかけを考えてみた
さて最初の方で「2025年の崖」は墓標のような存在であると、やや極端な比喩で表現したのですが、世間の関心は今でもDXにあるのだろうかと少々疑問を感じております。本来はトレンドであろうとなかろうと、ITであれビジネスであれ、進歩や改革は常に意識するべきで、一過性のブームで済ませてしまってはいけないはずです。経産省が危機を指摘したのは良いきっかけだったのは間違いないのですが、時間の経過と共に世間の関心事は次第にDXから離れて、生成系AIといったより新しいテーマにシフトしてきているようにも感じることがあります。私の感覚が間違いであればと願うのですが、DXは永遠のテーマだという意識は頭のどこかに常に置いておきたいものです。
ではまた