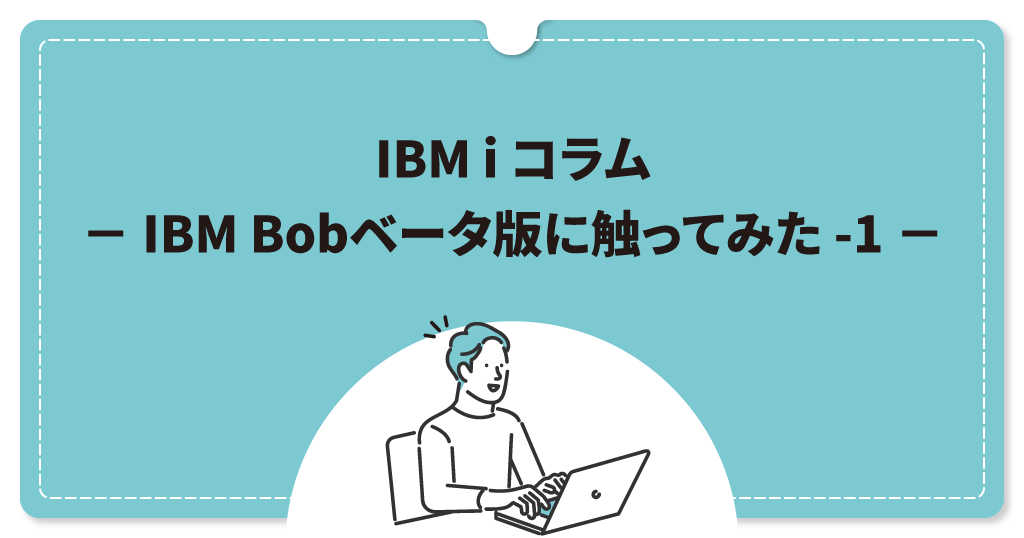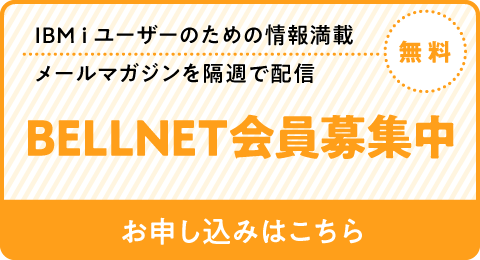IBM i のウンチクを語ろう:その67
- DXレポート2.1を読んでDX推進のきっかけを考えてみた -
皆さん、こんにちは。先の8月31日に公開されたのですが、Power10とか量子コンピュータの方に興味が移ってしまい取り上げるのが少々遅れてしまいました。ご存知「DXレポート2.1」です。経済産業省発行の一連のレポートの本編は2018年9月7日に公開され、「DX」や「2025年の崖」という言葉を世間に浸透させると共に、日本のDXが進捗しない現状に警鐘を鳴らしました。その後2020年12月28日に発行された続編は、DXとはレガシーシステムの刷新の事だという認識は誤りであると指摘する一方で、企業はDX推進のためにどのように取り組んでゆくべきかを述べています。これらについてはこのコラムでも都度取り上げており、本編は「「2025年の崖」を乗り越えよう」、続編は「DXレポート2を読んでみた」において紹介しています。もしよろしければ振返ってみていただければと思います。
先の8月に公開されたばかりの最新レポートは続編の追補版です。DXが目指す産業のあり方を示しながら、企業が変革を進めようとしない現状を「低位安定」と表現し、できだけ早いタイミングでDXへの取り組みを開始するべきであると主張しています。レポートそのものは、段落分け、箇条書き、図表挿入など、以前よりもメリハリの利いた表記になっており、全24ページと分量的にも大分読み易くなった印象があります。
「低位安定」とは従来からIT業界に見られる、ユーザー企業とベンダー企業の間にある相互依存関係を指しています。ユーザー企業はITをコストと捉えており、ビジネス要件が生じると複数のベンダー企業からの提案を募り、競争させてコストの削減を図ります。ベンダー企業の方は要件を実現するための提案金額をできる限り抑制し、運良く受注できれば低リスクで長期的な受託による収入を見込めます。両者は互いの利害が一致する、ウィンウィンの安定した関係にあります。

この安定状態を「低位」と表現しているのは、DXの進展は期待できそうにないことに理由があります。ベンダー企業への委託が「丸投げ」になりがちなため、自社システムであるにも関わらず、ユーザー企業はその中身がわからなくなる、すなわちブラックボックス化させてしまうリスクが生じます。一方ベンダー企業にとっては、得る対価は投入される労働量に基づいて決定されますので、労働量削減すなわち生産性を向上させようという動機はなかなか生まれません。また競合の中で案件を獲得するために、提案金額すなわちコストを抑制する必要が生じますので、大企業を頂点とするピラミッド型の多重下請構造に頼りがちになります。
さらにDXに対するジレンマも3点ほど指摘されています。
- 危機感のジレンマ: 業績が好調なうちに変革を進めることが望ましいが、危機感を覚えることがない。逆に危機感を覚える頃には投資余力が無くなっているために、変革を実行できない。
- 人材育成のジレンマ: 時間をかけて習得した頃には、最新技術は陳腐化している可能性がある。迅速に新技術を習得できる人材は、より良い条件を求めて流出してしまう。
- ベンダー企業特有のビジネスのジレンマ: ユーザー企業の丸投げ体質が改まり変革のための内製化が進むと、ベンダー企業の売上規模は従来の受託ビジネスに比べて縮小してしまう。

これらジレンマを打破して低位安定から脱却するには、DXに向けた経営層の積極的な関与が必要であるとレポートは述べています。そして丸投げされた事だけをやる「低位安定」関係と、それを支える多重下請け産業構造にあるベンダー企業が、変革を経ることによって以下の4パターンに向けて進化するだろうと述べています。産業のあるべき姿というわけです。
- ビジネス的側面からユーザー企業の変革を支援するための、コンサルティング的な役割を担うパートナー ユーザー企業と共に歩むという意味を込めて、レポートではこのような形態を「伴走支援」と呼んでいます。
- 変革を進めようとするユーザー企業に対して、最先端技術などの支援をおこなうパートナー これも「伴走支援」のもう一つのパターンであるとしています。
- 協調領域、すなわちユーザー企業にとって個々の強みとは関係の薄いアプリケーション領域に着目し、業界ごと、または業界横断型の共通プラットフォームを提供する企業 例えば総務系アプリケーションやグループウェアをSaaS型クラウド上で提供する企業は、このケースに該当すると考えられます。
- 新たなビジネス・サービスを提供する企業 様々なサービスをコンポーネントとしてプラットフォーム上に取り揃え、これらを組み合わせることでユーザー企業が新たな価値を迅速に生み出すことを可能にします。例えばIBM Cloudはこれの典型だと思います。
本編・続編・追補版と一連のレポートは、変革を進めないことでもたらされる危機や、変革を進める際の考え方を述べるだけでなく、経営層は積極的に関与する必要があるとも主張しています。これらの内容は至極真当なものだと思いますし、否定的意見を聞いたことがありません。ただ、何をもって変革に踏み切るためのきっかけにするべきか、という点はあまり明確には述べられていません。実際のところDXを実践している企業というのは、どのような動きをしているのかがわかると参考になるかもしれません。
日本のDXの現状をまとめたレポート「DX白書2021」が参考になりそうなので目を通してみました。IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が先の10月11日に公開した文書で、どなたでもPDFファイルをダウンロードし読むことができます。DXへの取組み状況、外部環境変化をビジネス・チャンスとする俊敏性、人材の確保や学び直しの取組みなど、ありとあらゆる観点から日米の事情が比較されており、これでもかという程に日本における課題が具体的数値をもって突き付けられています。400ページ近くもの分量があるので、ポイントだけを手短に把握するのであれば20ページのエグゼクティブサマリーでも用は足りますが、目当てのDX事例は本編にのみ掲載されています。

14件の事例は企業インタビューとして挿入されています。DX推進のきっかけになっているのは何だったのかという意識を持って、これらに目を通してみました。DX推進組織を作った、元々改革に対して前向きな企業風土があった、人材を揃えた、などといった要素はありますが、本を正すと結局は社長を始めとする経営層のリーダーシップに尽きていることがうかがえ、それ以外のきっかけらしきものは見当たりません。
DXレポート2の中で明確に述べられているように、DXの本質は企業文化の変革ないしレガシー企業文化からの脱却にあるので、実践するとしたら全社的取り組みになるはずです。経営層のリーダーシップが求められるのは必然であり、スキルを備えた人材や組織がそれを支える、という事例に見られる構図は当然のことなのでしょう。何かわかり易いきっかけらしきものがあればと思ったのですが、思惑は外れてしまいました。
DXという言葉が世間に浸透するにつれ、「守りのDX」とか「現場のDX」といったバリエーションを見聞きする事も多くなりました。これらは旧来から言われているIT化の促進であったり、モダナイゼーションの言い換えに過ぎなかったりする事も多いようです。言葉本来の趣旨からすると矛盾をはらんだ表現ですし、そもそもDXレポートに登場する用語ではありません。だからと言って原理原則に固執するだけでは何も進まないのも事実でしょう。一概に否定するのではなく、これらはDXへの第一歩を踏み出すきっかけと捉え、いずれ「化学反応」が起きることを期待しながら、地道にDXを訴求してゆこうと考えております。IBM i のユーザーにはIBM i を活用したDX実践方法があるはずですし。
ではまた。