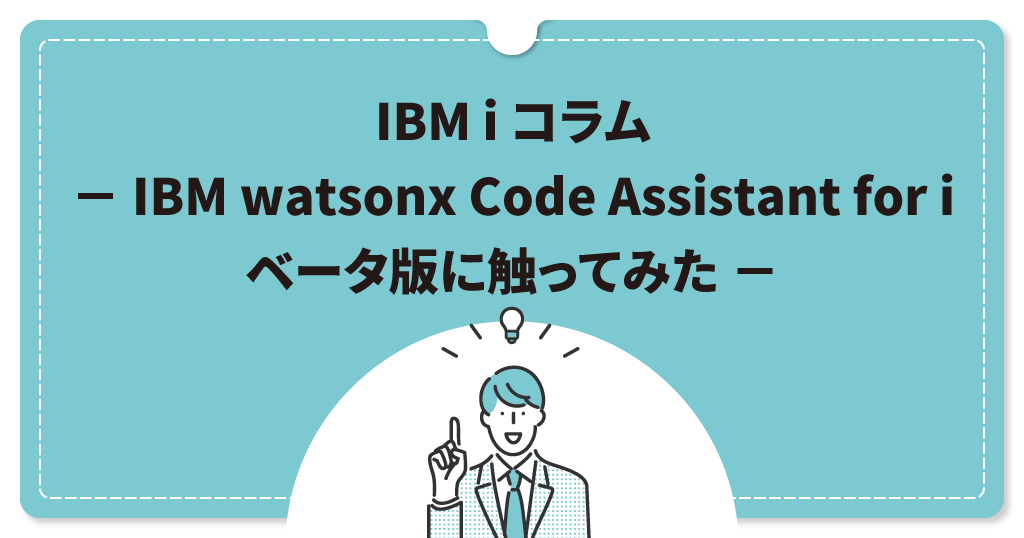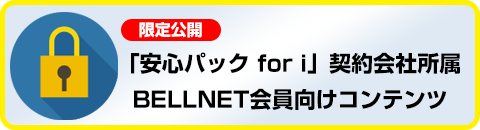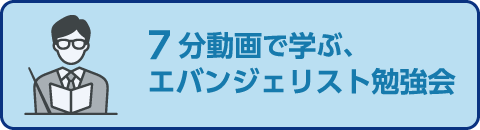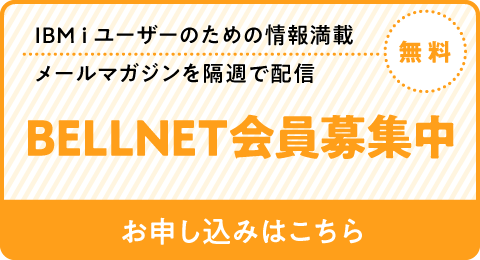IBM i のウンチクを語ろう:その104
- AIが変革する2025年のIBM i -
皆さん、こんにちは。AS/400が発表された1988年以降のITの歴史を俯瞰してみると、転換点と言って良い出来事がこれまでにいくつかありました。一つは1990年代のインターネットの普及であり、単なる高速・広域・無償のネットワークの普及に過ぎないという言い方もできますが、実際には文字通り世界中のビジネスのやり方や人々の生活を大きく変化させるほどのインパクトがありました。IBM i のテクノロジーについては、1995年の48ビットCISCから64ビットRISCプロセッサへの移行が大きな転換点だったと思います。この顛末については当コラム「過去30年の間に最も大きく変わったもの」のパート1とパート2にありますので、参照いただければ幸いです。そして2025年になって、私達はIBM i の新たな転換点を迎えつつあるのではないかと考えています。背景にあるのはAIであり、IBMから出てくる様々なメッセージも、AIによるIBM i の変革を示唆しているようです。
IBMが何を言っているのか具体的に見てみましょう。
昨年10月21日に「Code Assistant for RPG」(RPGコード・アシスタント)開発意向表明が出されました。開発意向表明とは通常の製品発表とは異なり、製品の方向性を公に示すことを狙いとする発表の一形態です。厳密にはコミットメントではないので、実現されるとは限らない旨の注釈が必ず付きますが、私の記憶する限りこれまでに反故になったことはありません。そしてRPGコード・アシスタントとは生成AIソリューションであり、以下の3つの観点からIBM i のアプリケーション開発者を支援する機能を提供するとしています。すなわち、既存RPGコードの理解を支援し、自然な文章記述に基づいてRPGコードを生成し、RPGコード用のテスト・ケースを自動生成する、というものです。意向表明の文面には明確に表現されていませんが、裏にあるのはFF RPGをより一層市場に浸透させることです。そしてタイムラグは生じると思いますが、他の機能を実現する可能性もあるようです。

これまでも述べてきましたように、RPGにはRPG/400(RPGⅢ)、ILE RPG(RPGⅣの初期の固定フォーム版)、FF RPG(機能強化されたILE RPGであるフリーフォーム版)の三世代があり、最新のFF RPGのシェアが次第に増えてきています。一方Fortra社による2024年のIBM i 市場調査結果を見てみると、新規開発において使用されているプログラム言語の89%をこれらRPGファミリー全体が占める一方で、IT部門はアプリケーションのモダナイゼーション(現代化)とIBM i スキルの不足という課題に直面していることが明らかになっています。そこでIBM独自の大規模言語モデル(LLM:Large Language Model)であるGranite(「花崗岩」の意)による生成AIを活かすことで、これらを一気に解決しようというわけです。
大規模言語モデルと言えばOpenAIのGPT-4やGoogleのGeminiなどが有名ですが、スタンフォード大学の基盤モデル研究センターのレポート「The Foundation Model Transparency Index Total Scores」において、Graniteは透明性が高いモデルのトップ5にランクインすると評価されています。モデル自体は巨大なブラックボックスなのですが、透明性とは、どのようなデータを使って事前に学習しているのか、どのようなチューニングが施されているのか、入力したデータがどのようにして使われるのか、などといった点がユーザーに見えることです。安全性や信頼性に関わるので、特に業務用途においては重視される傾向があるようです。良く知られているGPT-4やGeminiの透明性スコアがかなり低いのは私にとって意外でしたが、企業用途ではないのであればあまり問題にはならないのかもしれません。
では開発意向表明の裏側で、開発部門は具体的にどのような取り組みを行っているのでしょうか。その手順は大雑把に3つに分かれています。
最初にモデルの文章読解力を活かして、各種のマニュアルや書籍を読み込ませ学習させます。次の段階では、モデルの微調整を行うために、学習データをペアにして読み込ませます。ペアには3つのタイプが想定されており、一つはプログラムとその説明文のペアで、プログラムの説明の仕方や、文章に基づいてプログラムを生成する方法をモデルに学ばせます。また、プログラムとそのテストを行うためのプログラムのペアを読み込ませることで、様々なプログラムのテストの仕方を理解させます。そして同じことを実行する新旧のプログラム・ペアを読ませることで、モデルに新しいプログラムへの変換方法を学ばせます。最後の段階ではペアにはこだわらずにできるだけ大量のプログラムを読み込ませて学ばせます。
人間に例えると、最初に教科書を読んで基礎を理解し、次に問題集を入手して実践的な状況を踏まえながら問題と解答とをペアにして学んで応用力を付ける一方で、大量の模範回答例を覚え込む、といったところでしょうか。

ちなみにRPGからJavaへの移行は、プロジェクトのスコープにはありません。プロジェクトのそもそもの狙いは、プログラム言語の変換ではなく、既存の言語の開発者人口を増やすことにあります。市場のデータを見てもIBM i にとってRPGは主力言語であることが明らかであるばかりでなく、Javaへの変換によって特にバッチ処理におけるパフォーマンスが劣化するリスクが考えられます。またJavaプログラムにおいては、バージョン・アップグレード時の資産継承性が無い、という懸念もあります。RPGとJavaの対比について詳しくは、当コラム「最近JAVAは元気なのだろうか」にありますので、目を通していただければ幸いです。
ここで視点を変えて、ハードウェアについても次世代を眺めてみましょう。ご存知の方も多くいらっしゃるものと思いますが、IBMは2024年11月13付けニュースルームの中で、2025年にIBM Powerを刷新するとコメントしました。具体的にはPower11プロセッサ搭載システムとAI推論のアクセラレータであるSpyre(スパイア)、そして上記のRPGコード・アシスタントの登場です。AIの観点からPower11プロセッサとSpyreの狙いについて見てみましょう。
AIのためのハードウェアと言えば、GPUの名を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。この名が示すとおり、元々はグラフィックス(Graphics)処理専用なのですが、AIと相性が良いために利用シーンが拡がったプロセッサです。NVIDIA社が圧倒的な市場シェアを占めていることは、メディアなどでもよく取り上げられていますね。そしてNVLinkというプロセッサ間の高速バスによって、Power8またはPower9プロセッサとNVIDIA社のGPUとを直接接続するIBM Powerモデルの存在を憶えている方もいらっしゃると思います。Powerプロセッサは汎用、GPUはAI演算専用アクセラレータ、といった具合にワークロードの内容によって処理を分担するシステムです。このあたりに関心のある方は、当コラム「NVIDIA社を取り巻くIT事情」に目を通していただければと思います。
その後のPower10、そして現時点では私の推測に過ぎませんがPower11モデルにおいても、NVIDIAのGPUを搭載することはありません。IBM PowerがAIに対する関心を失いつつあるのではなく、AIワークロードの処理の考え方が変化し、それに最適化されたハードウェアが実装されるようになることがその背景にあります。

一言AIと言っても、学習とその後の推論と二つの処理があります。そして実業務におけるリアルタイム性を重視するのであれば、学習よりもむしろ推論におけるパフォーマンス維持に目を向けるべきです。学習時にデータセンター内のGPUをネットワーク経由で利用するので構わないにしても、推論時にはデータの在処に近いところで処理を行う方が有利です。また、学習・推論共に内部では行列演算が行われますが、学習においては高精度のデータを処理する必要があるのに対して、推論ではそれほどの精度は要らない、むしろより大きなサイズの行列を処理できる方が重要だという違いもあります。例えて言うならば、解像度の高い画像で学習しておけば、多少粗い画像であっても対象物が何であるか判断することは可能だということです。学習用には高価なGPUが必要ではあっても、推論用ならばGPUはオーバースペックであり、廉価な専用プロセッサでも十分対応できるはずです。これが世間で言うところのNPU(Neural Processing Unit)です。
「Copilot+ PC」の名を聞いたことのある方もいらっしゃるでしょう。時に「AI用PC」と呼ばれることもあるようです。マイクロソフト社はCopilot+ PCであるための要件の一つとして、40 TOPS(Tera Operations Per Second)以上、すなわち1秒間あたり40兆回以上の処理能力を持つNPUを搭載することとしています。このように、データの在処に近いところでAI推論処理を行えるようにするべきだ、という考え方が、一般化しつつあるというるわけです。
Power10プロセッサにおいても、AI推論処理用のアクセラレータであるMMA(Matrix Multiply Accelerator)をコア内に4基搭載しています。詳細はわかりませんが、Power11においてもMMAは搭載されますし、さらにシステム内PCIe Gen5バス用にSpyreアクセラレータ・アダプターを搭載できるようにする見込みです。このSpyreの性能は300 TOPS以上とされていますので、Copilot+ PCを大きく上回る推論処理性能を発揮できるものと思います。
RPGコード・アシスタントにせよ、Power11のMMAやSpyreにせよ、IBM i はこれからAIと共に変革期を迎えようとしていることを感じていただけましたでしょうか。現時点では製品としての正式発表はなされていませんが、今後より詳しい情報が公開されましたら、このコラムでも随時取り上げてゆきたいと考えております。
ではまた