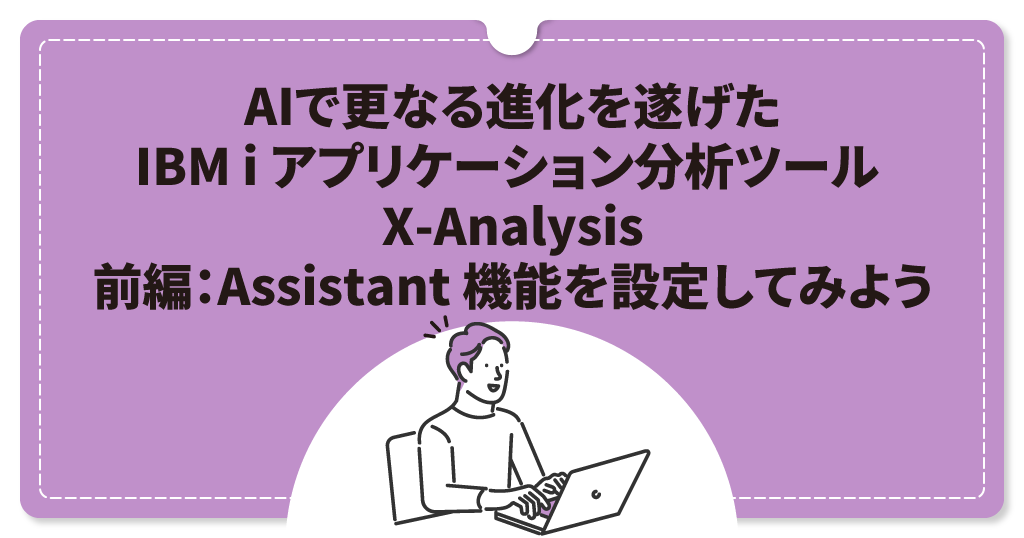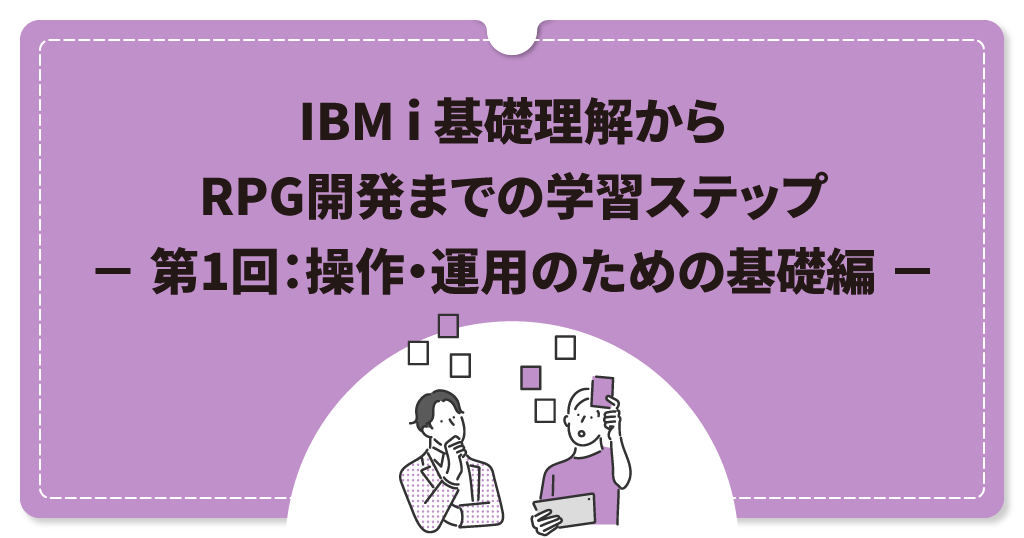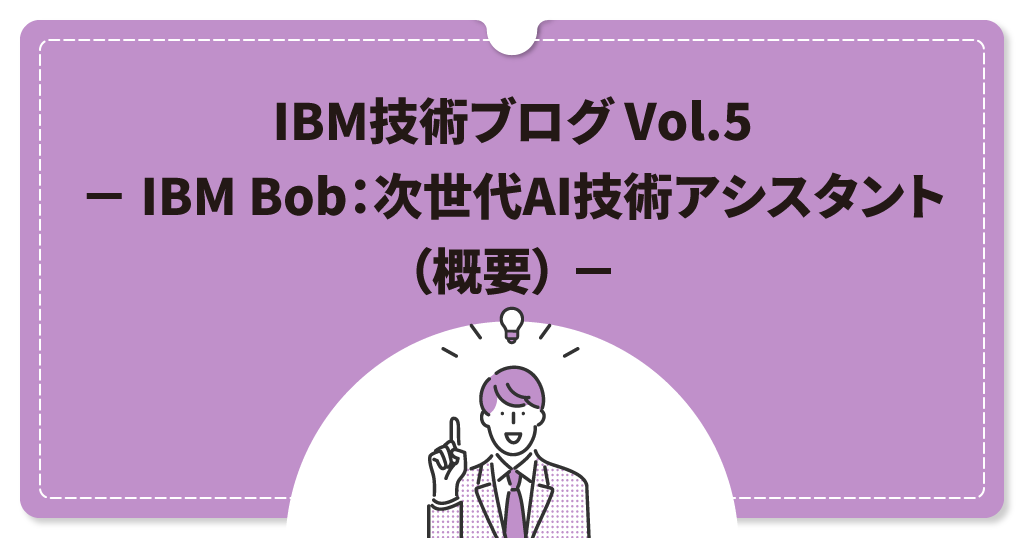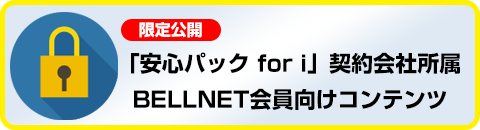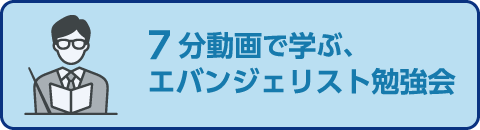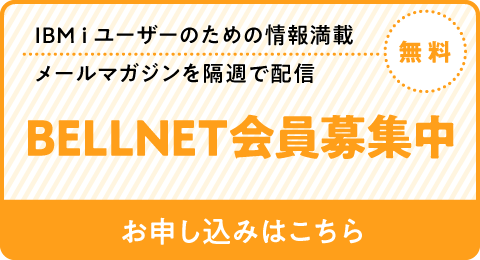RPG技術者不足を乗り越える - FF RPGでIBM i を次世代へ(第 4 章) -
第4章:FF RPG で描く基幹システムの将来
第3章「RPGⅢからFF RPGへの道程」(株式会社福岡情報ビジネスセンター、以下FBI)からの続き
短期的と長期的モダナイゼーション
これまでの各社の説明を通じて、既存RPGⅢアプリケーションのモダナイゼーション(テクノロジー刷新)を実現し、技術者不足を回避する上で、FF RPGが決定的な役割を担う可能性をご理解いただけたものと思います。この一連のドキュメントでは、RPGⅢからFF RPGへの全面的な移行事例、すなわち究極の姿としての長期的モダナイゼーションに着目しています。一方で一時凌ぎ的で最終解決策ではないかもしれませんが、そこまで本格的な取り組みを進めるための体制が整っていない、時間的制約がある中でDXを推進することが優先される、などといったビジネス上の事情から、短期的なモダナイゼーションを実施することも考えられます。両者の違いは既存プログラムの移行を前提とするか否かという作業負荷の大小によるものであり、短期的モダナイゼーションの事例件数の方が多いことは、どなたも容易に想像いただけるものと思います。ベル・データ自身もIBM i とAWSとのデータ連携実現による受注システム改善(株式会社エムエルシー様)や、IBM i とLINEチャットボットとの連携による受注システム刷新(日本サニパック株式会社様)、など多くのお客様におけるDX推進をご支援しています。
短期的モダナイゼーションの考え方
短期的モダナイゼーションの典型は、既存RPGⅢプログラムを前提に、FF RPGによる中継用プログラムを新規に開発し、インターネット上にあるSaaS型クラウド・サービスとの間で連携を図る、というものです。FF RPGとの連携のために、既存RPGⅢプログラムに多少手を入れる必要は生じますが、ビジネス・ロジックは概ね現行のものをそのまま利用します。
SaaS型クラウド・サービスは必ずしも独立した状態で価値をもたらすのではなく、外部すなわちお客様の既存の基幹業務システムと連携できることが求められます。このためにRESTと呼ばれる業界標準のインターフェースが用意されていることが多く、お客様のアプリケーションの世代やテクノロジーはどのようなものであれ、REST接続が可能であるならば利用できるサービスは実質的に無限になると言えるでしょう。旧来の基幹業務システムの閉鎖性を一気に解消する、いわゆるDXの早道でもあります。ただしRPGⅢプログラムのみでは実現できないので、別のテクノロジーを利用してREST利用のための中継機能を新たに用意しなければなりません。ベル・データではこれを実現するためのサービス・パッケージ「B-Core API-HUB」を提供しています。
このパッケージの内容は様々なコンポーネントで構成されており、お客様は個々の事情に合わせて内容を選択いただくことができます。ベル・データに全面的に開発を委ねていただくことも可能ですが、採用事例が多いのはお客様自身による内製を支援するための「内製化支援パック」です。お客様環境に合わせたFF RPGサンプルプログラムや、Q&A窓口を提供するものです。概ね若手技術者の方にとってFF RPGは馴染み易いというメリットはあるものの、ケースによってはいくつかのハードルを越えなければなりません。主なものは、インターネット環境におけるRESTによるプログラム連携は基幹業務を記述する際のそれとは作法が異なること、取り扱うデータタイプは未経験のJSONであること、などといったものです。サンプルプログラムやQ&A窓口は、これらハードルを乗り越える上で役立てていただけるものと思います。
一方で既存のRPGⅢやILE RPG初期版によるプログラムについては、REST中継用のFF RPGプログラムと連携させるために多少手を入れる必要があります。事例を見てみるとこの部分は概ねベテランの作業領域であることが多いようです。すなわち、長年RPGⅢに関わってきたベテランは、その知見を活かしながらRPGⅢの改修を担当する一方で、オープン系言語に比較的馴染んでいる若手は、その柔軟性を活かしながら新規FF RPGアプリケーション開発を担当します。新旧のテクノロジーと人材世代の複合的組合せであり、ベテランと若手の双方にとって比較的無理がありません。また大規模な移行作業とは無縁なので、検討開始から実運用開始に至るまでの期間が数カ月、といった事例も見られます。
長期的モダナイゼーションの考え方
モダナイゼーションは短期的に実現できるにもかかわらず、いずれは長期的な対策が必要となる理由はいくつか考えられます。FBIによる前章「RPGⅢからFF RPGへの道程」にあるように、RPGⅢを保守していた外部の会社が事業から撤退してしまうとなったら、待ったなしで移行作業を実施しなければなりません。これは極端なケースかもしれませんが、多くの会社でありがちなのは、かつてRPGⅢプログラムを開発し長年にわたって保守してきたベテランの退職です。そしてRPGⅢの要員を確保しようと人材を募集しても、人が来ないか来てもベテランのみ、になりがちです。この場合はあらかじめ期限を見通せるので、移行プロジェクトを計画するだけの時間的余裕を確保できることも多いでしょう。短期的モダナイゼーションのみでは解決にならないケースがあることを、是非認識いただきたいと思います。
RPGⅢとは言えソフトウェアですので、移行先のテクノロジー選択肢は理屈上無限にあります。JavaやC#でも不可能ではありません。今回紹介した事例ケースではFF RPGが選択されたわけですが、その理由をあらためて確認しておきましょう。
対象となるのは基幹業務を支えるためのアプリケーションです。すなわち全面刷新が頻繁に必要になることはまず考えられず、記述されたビジネス・ロジックは小規模な改良を伴いながらも長期的に利用されます。中には数十年に及ぶケースもあるでしょう。アプリケーションに比べれば、マシン本体やオペレーティング・システムの寿命は極めて短いのが現実です。アプリケーションはこれらシステムの刷新を乗り越えることができなければ、すなわちアプリケーション資産の継承が実現できなければ、システム刷新と同時に見直しを避けることはできません。また仮にビジネス上の事情によりアプリケーションの見直し頻度が高いものであったとしても、システム刷新と同期させなくてはなりません。両者は本来独立したものであるはずです。これらの煩わしさはオープン系システムの宿命ともなっています。そして無数にあるテクノロジー選択肢の中で、そのアーキテクチャや実績のいずれにおいても資産継承性が実現できる環境は、IBM i などのレガシー系システムのみだと言えるでしょう。
さらに既存のRPGⅢやILE RPG初期版によるプログラムを前提とするならば、ツールが整備されているFF RPGを移行先として選択するのが最も有利だと考えられます。システムの安定性やセキュリティなどの管理・運用の考え方は変わらないこと、ツールを活かすことで作業負荷を抑制できること、がその理由です。このあたりの判断の仕方は各社様々であるようです。中には冷静な評価を行う前に「脱IBM i」というコンセプトが先行してしまい、プロジェクトが暗礁に乗り上げてしまったケースもあります。ベル・データとしてはお客様の判断を最善のものにしていただくために、当文書の執筆社である三和コムテック株式会社、株式会社福岡情報ビジネスセンターの知見を活かしながら、個別に「IBM i の次を考える勉強会」を開催するなどしてご支援しています。
現時点では長期的モダナイゼーション事例は少ないが
FF RPGへの全面的な移行を実施したプロジェクト概要を紹介できるお客様事例は、現時点では希少です。製品概要や、移行ツールの機能と活用法に対する知見、プロジェクトの必要性理解とそのための体制整備、そして何よりも全体像を理解し、FF RPGへの移行が最善の策であるとしたお客様の判断がプロジェクトを成功に導いていると感じます。
事例に見るように、ツールがあるとは言え移行はある程度の規模のプロジェクトになることは、やむを得ないものと思います。それでもオープン系に移行し長期的にアプリケーションを維持・運用してゆくよりも、お客様にとっては有利な選択肢になると確信しています。IBM i に対する漠然とした印象に囚われず、必要であればシステムの正しい価値や位置付けを知る外部の知見を活用するなどして、お客様にとって最善の選択をしていただきたい、そして当一連の文書がその一助になればと願っております。
【 RPG技術者不足を乗り越える ~ FF RPGでIBM i を次世代へ 】
| 第1章(ベル・データ) | 「FF RPG への移行を検討するべき3つのポイント」 |
| 第2章(三和コムテック) | 「RPGソースをFF RPGに変換するツールARCAD Transformer RPGのご紹介」 |
| 第3章(福岡情報ビジネスセンター) | 「RPGⅢからFF RPGへの道程」 |
| 第4章(ベル・データ) | 「FF RPG で描く基幹システムの将来」(当文書) |
【 他社サイトを含む、あわせて読みたい記事 】
- iWorld
- FF RPG概要説明「IBM i の"新"必須言語 〜FFRPG入門〜(全 12 回)」
- FF-RPGハンズオン自習環境 登録申込
- ベル・データ
- IBM i と言えばRPG
- 基幹業務システムとクラウドとの連携を支援するサービス「B-Core API-HUB」
- 三和コムテック
- 福岡情報ビジネスセンター
- Qiita(技術ブログ)
- FF RPGサンプルプログラム「IBM CJ 2023 C06-020 FF-RPGサンプルコード Indexページ」
- 若手技術者による公開記事「IBM i RiSING (若手技術者コミュニティ)公開資料まとめ」