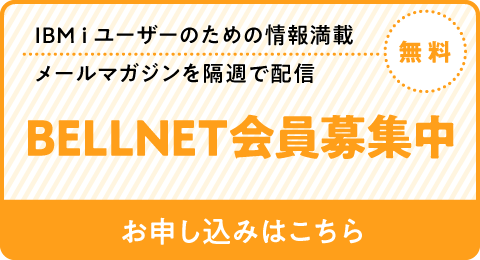「オールインワン」がもたらすIBM i の安定と運用負荷軽減
皆さんがご利用中のIBM i はどのようにして構築されたのでしょうか。オペレーティング・システムと周辺ソフトウェア込みのマシンをIBMの販売代理店経由で購入し、またはクラウド上のマシン利用を前提に、設定作業を経て、自社独自のアプリケーションとデータをインストールした、といったところでしょうか。より高度な機能を必要とする場合は、IBM製以外のパッケージ・ソフトを追加インストールするケースもありますが、多くの場合はIBM製ソフトウェアだけで一通りの機能を賄うことが可能です。
オールインワンとは何か
例えばデータベース・ソフトはオペレーティング・システムであるIBM i に標準的に組み込まれていますので、インストール時に何らかの導入・設定作業を行う必要はありません。そもそも「DB2/400」(現在の名前は「Db2 for i」)という名称は1988年当時のAS/400(同「IBM Power」)発表時には存在しておらず、OS/400(同「IBM i」)の機能の一部という位置付けでした。1990年代半ばになって、その存在を明らかにしておくべきだというマーケティング上の理由により、名前だけが後付けで出てきたものです。
これがオープン系だったらどうなるでしょう。選定するべきパッケージ・ソフトの種類と量は多岐に渡ります。データベース一つ取ってみても、製品を選定・購入しインストールするだけでなく、オペレーティング・システムとは別にユーザー登録などの設定作業を行わなくてはなりません。場合によってはオペレーティング・システムに対して、前提となるパッチ・プログラムをインストールするケースもあるでしょう。他の業務パッケージ・ソフトやバックアップ・ソフトなどにおいても同様の考慮が必要になるわけですが、パッチ・プログラムが互いに干渉しない保証はどこにもありません。データベース・サーバーやバックアップ・サーバーなど、念のために用途毎にシステムを分離するケースも珍しくありません。一通りのシステム機能を実現するために、複数の筐体または仮想マシンが必要になるというわけです。
独自アプリケーションとデータに関わる作業は避けようがありませんが、その直前状態に至るまでの作業量の大小は、言わばシステムとしての完成度を表していると言えるでしょう。究極の状態にまで完成度が高まっていること、必要機能一式が統合されていて直ちに利用できる状態にあることを、IBM i では「オールインワン」と呼び、最も重要なアーキテクチャの一つとして位置付けています。ちなみにご存知の方もいらっしゃると思いますが、IBM i の「i」は「Integration」(統合)に由来しています。IBM i イコール「統合」というわけです。
IBM i だけではないオールインワン
ただオールインワンを標榜しているのはIBM i だけではありません。システムとして追及するに足る価値であると認識されているためか、市場を見ればオープン系であってもオールインワンがあり、直ぐに使える状態のシステムであることを訴求しています。同じオールインワンでもIBM i のそれは他とは違う、という点を理解しておきたいと思います。
どのようなシステムであれ、「オールインワン」の状態に到達するには、膨大な数の各種コンポーネント(部品)を組み上げる必要があります。ハードウェアとしてのマシンとその部品だけでなく、オペレーティング・システムやデータベースなどのソフトウェア製品、さらにそれらを補完する機能やパッチ・プログラムまでも含みます。違いというのは、システムとして完成された状態に組み上げてゆく工程が、どこで誰によってなされるのか、という点にあります。
完成品と組み立てキット
IBM i の場合はIBMがメーカーとして、工場出荷の際にオールインワンを達成することを目指しています。開発部門は最終製品を想定して各部品を設計開発し、工場ではそれを目に見える形に組上げ統合します。当然のことながら、この一連のプロセスにおいて統合に向けたテストが行われ、相性の悪さが見つかれば修正されます。オールインワンという概念は、設計から出荷に至るまでのプロセス全体の中に組み込まれているのです。
オープン系における各メーカーの役割は、システムから見ると「部品」を自社製品として市場に送り出すことにあります。部品がきちんと機能することを検証するために、典型的なシステム構成を想定したテストは実施するでしょう。ユーザーは他にどのような部品を組み合わせる可能性があるのかを知り、あらゆるバリエーションを試すのは現実的ではありません。テストが網羅的ではないので、システムの安定性に影響が出る可能性があります。
ユーザーの方は既に市場にある各種の部品を多数組み上げてゆくことで、オールインワンの状態に到達しなければなりません。技術的なノウハウを必要とする作業であり、自力でこれを実施することは困難なので、多くの場合はインテグレータに作業を委ねることになります。
IBM i とオープン系は、完成品と組み立てキットに例えることができるでしょう。そしてノウハウを持って組み上げる作業を請け負うのがインテグレータの役割です。ちなみに英語のインテグレータ(Integrator)には「統合する人」という意味がありますので、名前そのままという感じですね。
| IBM i | オープン系 |

|

|
運用負荷か「塩漬け」か
当然のことながら、市場にある部品のメーカーが責任を負うのは自社製品に対してであって、ユーザーが利用する統合されたシステムに対してではありません。統合の過程で不具合が見つかったら、原因を切り分けた上で各部品メーカーに修正を要求することになります。この時に部品メーカーは自社製品の問題であることを認めれば修正に取り組みますが、そうでなければなかなか解決に向けた動きには至りません。原因の切り分けが決着しなければ、一時的に、運が悪ければ恒久的に、運用で「逃げる」しかなくなるかも知れません。結果的にユーザーに皺寄せが行くことになります。
無事にシステムとして組み上がり運用フェーズに入ったとしても、なかなか安心はできません。バグが見つかるかもしれませんし、部品毎に新たなパッチ・プログラムがリリースされるかもしれません。せっかく稼動しているシステムなので余計なことはしたくないと思ったとしても、製品の寿命には限りがあります。メーカーのサポートを受け続けるためには、どこかのタイミングでバージョン・リリースをアップグレードしなければなりません。頻度やタイミングはメーカーによってまちまちですし、その度に他の部品との互換性の懸念が再浮上することになります。業務を支えるためのITであるべきなのに、ツールそのものの維持が負担になってきます。
こうなると容易には手を出せないとして、メーカーの公式サポートの無いままにシステムを「塩漬け状態」に置いてしまうケースも生じます。オープン系でありながらも古いまま放置された状態、いわゆるオープン・レガシーという言葉を聞いたことのある方もいらっしゃるでしょう。
インテグレータ頼みのシステム
スキルや作業負荷を自力で賄えないとなると、初期のインストール時だけでなく保守・運用までも含めてインテグレータに全てを委ねた、いわゆる丸抱え状態になるケースも多いようです。これらは全てユーザーに対するコストとして跳ね返ってくるばかりでなく、自社システムの内容を理解しているのはインテグレータだけの状態、インテグレータ頼みのシステムになりかねません。インテグレータ・ロックインの状態にあると言えるでしょう。
IBM i であれば部品間の互換性の懸念は解決済みの状態にあります。現状のままにするのか、互換性が検証されている環境にシステム全体をアップグレードするのか、という選択になります。この際に考慮しておきたいのは、IBM i にはアプリケーション資産が継承される仕組みが備わっている、という点です。事前のテストを実施することは必要ですが、アップグレード時の作業は比較的シンプルなものになります。
安定性というメリット
手のかからないシステムは安定性をもたらすようです。ここで米調査会社であるITICによるレポート「ITIC 2022 Global Server Hardware, Server OS Reliability Report」を見てみましょう。IBMのホームページ経由でPDF版をダウンロードできますし、これの邦文解説記事「ITIC 2022年世界サーバー・ハードウェア、サーバーOS信頼性調査」がiWorldサイトに掲載されています。その中で特に着目したいのは、PDFのページ4に掲載されているグラフ「Exhibit 1. Unplanned Monthly Per Server Downtime in Minutes」です。これはシステム毎の月間計画外停止時間、すなわち障害によってシステムが停止してしまう時間を分単位で表したものです。理想はゼロであることは言うまでもないのですが、形あるものはいつかは壊れる可能性から逃れられないのも現実です。
最も信頼性が高いのはIBM Zの0.0043分、次いでIBM Power、すなわちIBM i が稼働するサーバー・ハードウェアの1分という結果が示されています。これらを含めて上位にランクインしているのは、単一メーカーが最終製品として仕上げて市場に提供しているものです。逆にオープン系は停止時間が長目であることがわかります。どうやら統合性は信頼性である、と言えそうです。
統合型システムだけでなくオープン系にも考慮点はある
IBM i のような統合型のシステムはオープン系を凌ぐ、とシンプルに言いたいところではありますが、考慮事項もあるのが現実です。よく指摘される懸念は、製品(システムにとっての部品)選択の幅が狭いのでメーカー(ベンダー)・ロックインになり易い、結果的に製品の価格決定権はメーカーに握られてしまうので高い買い物になってしまう、というものです。そして新テクノロジーが登場したとしても、当のメーカーがそれを採用しなければ、自社システムの進歩は望めなくなってしまいます。
市場にある部品のバリエーションの大きさ、という意味ではIBM i の方がオープン系よりも小さいのは致し方無いとも言えます。オペレーティング・システム搭載の標準機能だけで必要機能が概ね賄われるので、需要はあまり大きくありません。例えばDb2 for i が既にインストール済みであるにも関わらず、好みのデータベース・ソフトを別途使おうと考える方は、いたとしてもごく少数に留まるでしょう。そもそもオープン系においても、ユーザーは幅広い選択肢の中から、自ら主導して各製品を吟味・比較し、選択されているのでしょうか。インテグレータに提案を求め、システム構築のノウハウが多くて安全性が高いから、という理由で推奨された製品を選定していないでしょうか。
新テクノロジーの採用においても同様のことが言えます。利便性の高そうな新製品・新機能が登場したとしても、実際に利用する機会を得られるかどうかは、インテグレータの判断に大きく左右されます。未だ安定していない試作的な機能を本番環境に採用するわけにはいかないと考え実装を見合わせるかもしれませんし、充分に経験を積んでいるので問題無く実装できると判断するかもしれません。
IBM i のテクノロジーは進化しているのでしょうか。このあたりはユーザーの方に判断を委ねたいと思います。ただ一つ言えることは、市場から撤退する製品が相次ぐ中、過去35年にわたる進化の積み重ねが現状に至っており、将来性を担保しているということです。私の理解では転機は1990年代半ばにありました。それまでのレガシー的なオフコンの位置付けにあったAS/400は、オープン性を備えることでクライアント・サーバー環境におけるサーバーとしての機能を追求する、と大きく舵を切りました。求められる性能も大きく変化することを見越して、従来のCISCプロセッサからRISCへと転換を図っています。その後のインターネットやクラウドとの連携など、更なるオープン化の足跡はご存知のとおりです。
詰まるところシステムは誰かにロックインされる
メーカー(ベンダー)・ロックインという言葉があります。選択できる製品機能も、その後の自社ITの進歩も、コストも何もかもがそのメーカーに縛られてしまう状態(リスク)を言い、一般的には避けるべきとされています。メーカー・ロックインを避けるために、オープン系を選択した方が良いという主張もあります。確かにオープン系ならばメーカー・ロックインにはなり難いでしょう。
何となくわかっていながら敢えて触れないようにしているためなのか、見落とされがちなのが、インテグレータ・ロックインの可能性です。選択できる製品機能も、その後の自社ITの進歩も、コストも何もかもがそのインテグレータに縛られてしまう状態(リスク)です。あまり話題に上る言葉ではありませんが、存在していることは間違いありません。メーカーとインテグレータと、どちらのロックインの方がユーザーにとっては都合が良いのか、何とも言い難いように思います。どのみちロックインは免れないのであれば、メーカーであれインテグレータであれ、言葉にこだわるのではなく、最適なパートナーを選べば良いのではないでしょうか。
IBM i は安い買い物か
コストについても検討してみましょう。同等機能を備える製品であっても、市場規模が小さければそれだけ割高になるのは市場原理であり、その意味ではIBM i 関連の製品はオープン系に比べてコスト高の傾向にあることは否めません。ただ、個々の製品ではなく、システム全体の視点から把握したらしたらどうなるでしょうか。安定性や運用性など、IBM i のような統合型システムにはオープン系では得難いメリットがあることをこれまで説明してまいりました。これらが損なわれたら、人が何らかの形で作業を行わなければなりません。詰まるところは製品と人の作業コストとどちらが大きいのか、システムに関わるコスト全体、すなわちTCO(Total Cost of Ownership: 総所有コスト)ではどうなるのか、という視点が必要になります。そして様々な分析結果によると、ITコストの中で最も大きな割合を占めるのは人件費です。ユーザー毎に状況は異なるので金額を一概に数値的に表現することはできませんが、IBM i はTCOが低いシステムであるとよく言われています。
もう少し具体的に見てみましょう。どのくらいのIBM i ユーザーがIBM i をROI(Return On Investment)、すなわち投資対効果に優れるシステムと見なしているのか、Fortra社によるサーベイ結果があります。2023年版のレポートによると、IBM i のROIは他のシステムよりも優れているとしたユーザーの割合は、90%を切ったことは過去に無いこと、最新の結果では95%に達していることが報告されています。IBM i は安いのです。必ずしもオールインワンという特性だけがこの結果に寄与しているわけではありませんが、IBM i のメリットとして評価できるのではないでしょうか。
- 7 分動画による解説「他とは違う IBM i の All in One」
| 前章「安全性を追求するIBM i の「セキュリティ」」へ | 「IBM i とは」TOP | 次章「IBM i のユニークなファイルシステム「単一レベル記憶」」へ |